歳時記
京都職人 俳句逸楽
西陣
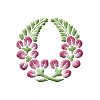 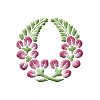 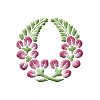 西陣歳時記 〜 紅恥庵の西陣案内 〜 |
西陣で生まれ育ち、70を超える現在まで現役職人として活躍する、西陣を知り尽くした紅恥庵氏が伝えたい「西陣歳時記」 小さな町にこれだけぎっしり日本の文化がつまっているのは、とても興味深い。 西陣の面白さ、奥行きを少しでも感じていただければ幸いです。 |
TOP
職人の仕事場
京都西陣案内
西陣 町の写真
西陣 町の写真2
俳句のページ
俳句のページ2
書籍 俳句集『恋猫』1
『恋猫』2
リンク集
| 1月 初詣 西陣の大半の地域を占めて氏子とする今宮神社に訪れる人が多い。 初天神 学問の神様の天神さんの総本社の北野天満宮は受験生も含め、初詣から25日の初天神まで30万人の初詣客が訪れる。 この頃ろう梅が咲き始める。 |
 今宮神社 |
| 2月 節分 千本釈迦堂(大報恩寺)では、おかめ節分といって、おかめの面をつけて鬼やらいをする。 梅花祭 北野天満宮では25日に梅花祭が開かれ、上七軒の芸妓たちのお点前がある。 |
 おかめ塚 |
| 3月 人形展 堀川通り寺ノ内にある宝鏡寺で雛祭りの人形展が開かれる。 平安時代の五節の舞が奉納され、献茶、献花が行われる。(3月1日〜4月3日) |
|
| 4月 桜 北野天満宮の西にある平野神社は45種の桜が咲く古くからの名所である。 平野神社 やすらい祭 第2日曜に今宮神社で開かれる花鎮めの神事で、長和三年(1014年)京都で疫病の大流行があり、これを鎮めるために行われた神事が始まりである。 今宮神社の参道にある二軒の茶店のあぶり餅は西陣の名物。 北野踊り 北野天満宮が建立された時に、余った材木で作られた茶店から始まった。上七軒の芸妓、舞妓による舞踏激。(15〜25日) 蹴鞠 白峯神宮の末社で蹴鞠を大成した飛鳥井家の守護神を祀っているところから、平安時代の鞠衣装に身を包んだ人が蹴鞠を奉納される。 (4月14日) |
  蹴鞠 |
| 5月 ゑんま堂狂言 京都三大念仏狂言の一つである。殆どの演目に台詞がある。 (5月1〜4日) 今宮祭 紫野今宮神社の祭礼で、5日〜第三日曜日にある。 やすらい祭より古く、長保三年(1001)五月に疫病の流行を鎮めるため、朝廷の命により建立され、御霊会が行われる |
  ゑんま堂狂言 |
| 6月 夏越の祓 水無月の祓い 上半期の穢れを祓い、下半期の無病息災を願って行われる行事で、各神社で大きな茅の輪を作り、それにくぐる事で厄落としできる。 西陣の今宮神社、北野天満宮、船岡山にある建勲神社や陰陽師で名高い晴明神社などで行われ、この日に三角形のういろうの上に小豆を散りばめた菓子を30日に食べる風習がある。 これは夏に氷を食べると夏痩せしないと信じられていたのだが、氷は貴重でその代りに氷に似せて作られたお菓子である。 |
 船岡山の茅の輪  |
| 7月 風祭 七夕 千本ゑんま堂で夏の夜間特別拝観が行われる。 梶の葉に願い事を書いて祈祷し、その葉が月に照らされると願い事が叶うと言い伝えられている。 (7月1日〜16日) |
 写真素材 (c) NOION |
| 8月 大文字の送り火 京都の盂蘭盆会で精霊を送る行事である。 西陣でも各々見えるところはあるが、中でも船岡山からは、大文字、妙、法、船形、左大文字と鳥居以外全てを見ることが出来る。 地蔵盆 西陣の各町内に祀られているお地蔵さんの縁日で、各町内ごとに23日か24日に子供を中心として行われる。 |
 |
| 9月 桔梗 紫野大徳寺は大燈国師宗峰妙超が正和四年(1315)に赤松則村の帰依を受け建立したのだが、住持に、一休(1349〜1481)、澤庵(1573〜1645)が有名であり、三門の金毛閣は利休像を上層に置いた事から秀吉の忌憚にふれて、後の切腹につながる事で名高いが、塔頭の一つの芳春院の庭は桔梗の花で埋め尽くされて見事である。 |
| 10月 瑞饋(ずいき)祭 北野天満宮の五穀豊穣に感謝するお祭。神輿の屋根はずいき作り。他の各部に野菜や湯葉、麩などで飾られている。 (10月1日〜5日) 銀杏 堀川通りの今出川から鞍馬口までの間、中央分離帯に大樹となった銀杏並木が続いて見事な景である。 実がこぼれると、これを拾う人の姿が見られる。 金木犀 宝鏡寺は門跡尼院で、百々(ドド)御所と呼ばれている格式の高い寺である。「人形寺」とも呼ばれている。 寺を入った正面に大きな円く刈り込まれた金木犀と銀木犀があり、芳香を放して迎えてくれる。 |
 金木犀 |
| 11月 紅葉 金閣寺 足利義満によって北山殿として建てられ、死後、夢想国師により開山されたのだが、創建以来残っていた金閣も昭和25年(1950)に放火により焼失したが、5年後に創建当時の姿に復元された。庭園は平安時代を模した名園である。 |
 |
12月 大根炊 千本釈迦堂で境内の大釜で聖護院大根を沢山炊いて信者にふるまわれる。 (12月7日〜8日) 終天神 毎月25日の最終の市で、境内には陶器、古書、書画、骨董、食べ物、道具類、植木等々あらゆるものの露店が立ち並び正月用品等を求める人で大変な賑わいを見せる。 除夜の鐘 西陣に限らず、京都ではどこの寺院でも除夜の鐘が撞かれて、過ぎし今年を感謝し、来る新年の幸せを祈る事になる。 |
 大根炊  千本釈迦堂 |